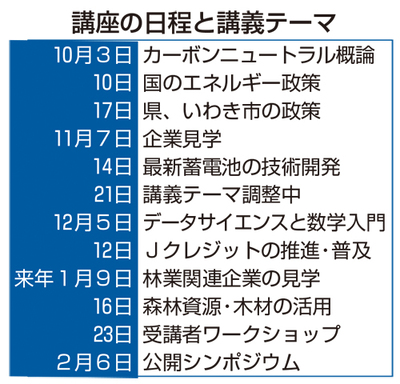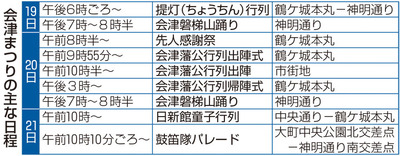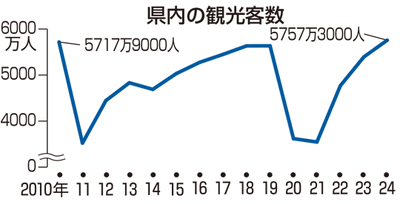日本酒の原料となる酒造好適米の価格が高騰し、蔵元の経営に重くのしかかっている。コメ不足から続く主食用米の価格高騰のあおりを受けた形で、蔵元からは「近年まれに見る価格の上がり方で、対策が追い付かない」と悲痛な声が上がる。「酒どころふくしま」を守るため、福島県は蔵元に酒米購入費の一部を支援する方針だが、米価の先行きが見通せないだけに、蔵元は商品の値上げや分量の見直しなど苦渋の選択で難局を切り抜けようとしている。
「酒米の値段が2023年産から倍くらい上がっており、費用は数億円単位で増えた」。会津にある蔵元の担当者は厳しい現状を明かす。商品を値上げせざるを得ず「主食用米の値段も高止まりする中、消費者にどの程度受け入れられるのか…」と表情を曇らせた。
地酒「千功成」の醸造元・檜物屋酒造店(二本松市)は県産酒造好適米「夢の香」と「美山錦」を原料に使用しているが、本年産はいずれも前年産より1.7倍ほど値上がりした。斎藤一哉社長(54)は「農家との直接取引ではなく県酒造組合を通して一括で購入しているので、仕入れ価格を交渉することもできない。県の補助金を活用しても大変厳しい状況だ」と苦悩する。
長引く物価高を受け、同社は4月に商品を10%値上げしたばかりだが、さらなる米価高騰で価格転嫁が追い付かない状況という。出荷が本格化する中、再度の値上げはできず、従来の1.8リットルと720ミリリットルに加え、価格を抑える方策として大吟醸酒などの高級酒を新たに300ミリリットルサイズで販売することを検討する。斎藤社長は「少しでも手に取りやすくし、消費者離れを食い止めたい」と話した。
生産者支援「さらに手厚く」
県酒造組合は酒米を各JAやJA全農福島を通して購入し、ほぼ同価格で各蔵元に販売している。仕入れ値は毎年、コメの生産者に前払いする「概算金」が出た時点の単価を参考に全農と協議して決定するが、今年は前年産比で60キロ当たり平均1万2000円程度はね上がった。昨年も2000円ほど上がったものの、担当者は「今年はこれまで例を見ないほどの値上がり。さすがに高過ぎる」と頭を抱える。
組合によると、主食用米と比べて酒米の価格が安いと転作する生産者が出かねず、主食用米と足並みをそろえることで酒米の生産離れを防ぐという。
ただ、米価の上昇分を全て販売価格に反映すれば消費者が購入を敬遠してしまうため、転嫁できない分が赤字として積み上がり「売れば売るだけ損する」状態にもなりかねない。渡部謙一会長(60)は「造りの縮小や精米歩合を変えるなど工夫を強いられる蔵も出てくるはずだ。日本酒離れが叫ばれる中、さらなる懸念材料になる」と苦しい胸の内を語った。
こうした危機感から県は9月補正予算案に2億1700万円を盛り込み、前年産米から本年産米の価格上昇分のうち、最大で半額を補助する方針だ。蔵元の仕込み前に支援策を示すことで「ふくしまの酒」のブランド力維持を目指す。
会津の蔵元の担当者は県の補助を「少しは足しになる」と感謝し「農家への補助も手厚くしないと、酒米を作る農家が減ってしまうのではないか」と生産者への支援を求めた。