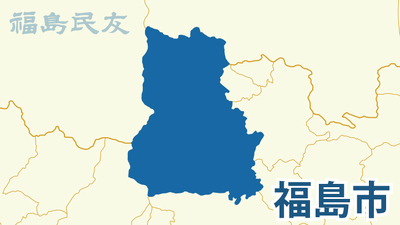1945年8月15日、ラジオの玉音放送(終戦の詔勅)は、31年の満州事変に始まる15年に及ぶ戦いの終わりを国民に告げた。県によると、37年に始まった日中戦争から太平洋戦争が終わるまで、県内出身者6万6000人余りが戦死した。
犠牲となったのは兵士だけではなかった。開拓団員、輸送船の船員、看護婦などの立場で戦闘に巻き込まれた県民も少なくなかった。戦火は県内にも広がり、各地が空襲を受けた。戦争末期の45年4月には郡山市に米軍機が来襲、若い学徒動員生を含む460人が亡くなった。7月にはいわき市平に、約5トンの模擬原爆が落とされ、平第一国民学校(現平一小)を直撃した。
福島市の県護国神社には、戦没者の生きた証しが刻み込まれたいくつかの石碑が並ぶ。14日は強い日差しに照らされた碑を見上げ、犠牲者に思いをはせる参拝者の姿があった。
戦後80年、戦争体験者が少なくなり、記憶や教訓を語り継ぐことが難しくなりつつある。15日は多くの県民が、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて心に刻み、世界で今なお絶えることがない戦争に苦しむ人々に心を寄せる日となる。