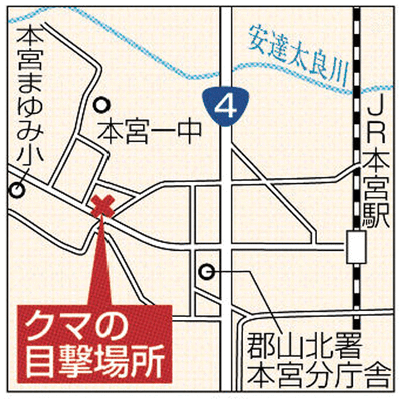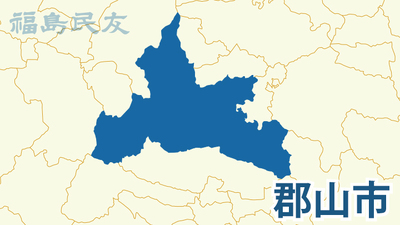ロボットやドローンの技術を競う国際大会「ワールドロボットサミット(WRS)2025」は10~12日、南相馬市で開かれる。大会の目的は災害時に活躍するロボットなどの技術開発。「今後起きる災害の被害やリスクを減らしたい。それが自分たちにできること」。ドローン開発のハマ(南相馬市)の社長金田政太さん(41)は東日本大震災からの復興に取り組む福島の地から、技術の発信に力を注ぐ。
ドローン技術、高める契機に
ハマ(旧スペースエンターテインメントラボラトリー)は2017年、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト構想)の下、浜通りで活動を始めた。復興という共通の願いに向かって頑張る浜通りの人々に囲まれての研究開発は刺激になった。そしてさまざまな機会に震災で経験した苦労を聞き、災害の大変さが身に染みた。
「災害が起きた時の大変さを和らげたい」。そんな思いを抱え、ハマは能登半島地震で支援に当たった。陸路が遮断された被災地で、ドローンを使い漁港の被災状況を撮影した。一方で普段飛ばしていない場所での飛行に「地形は電波にどう影響するのか。その対策は」「最小限の荷物でどう飛ばせるのか」―。平時からシミュレーションし、備えておかなければいけないことも分かった。
ハマはWRS初参加で、金田さんは所属する南相馬ロボット産業協議会と会津大の合同チームでリーダーを務める。
大会では能登半島地震と同様に、地割れや海岸の隆起で陸上や海から接近できず、残されたのは空だけという状況の中、遠隔でドローンを使った被災状況の把握や建物内での捜索の技術などを競う。建物内に入る小さなドローンをぶら下げる分離機構は熱い思いを持った浜通りの仲間たちが製造した。
「お世話になった浜通りと一緒にこれからも発展したい」と願う金田さん。社名のハマは浜通りの”ハマ”であるとともに、災いを打ち破る破魔矢の”ハマ”でもある。「実際に災害が起きた時、すぐさま運用するのは難しい。災害を想定した大会に臨むことで、改良点を見つけ、技術や運用の開発につなげたい」と力を込める。
ユーチューブで生中継
WRS2025には、4部門に国内外の大学や研究機関から39チームが出場。本県からはハマも所属する南相馬ロボット産業協議会と会津大でつくる2チーム、会津大単独の2チームが挑む。
福島国際研究教育機構(エフレイ)の主催、経済産業省の共催。南相馬市での開催は2021年以来。ドローンを使った物資の搬送のほか、工場災害を想定したロボットによるメーター数値の読み取りやバルブ操作などの技術を競う。競技は一般公開され、動画投稿サイト「ユーチューブ」で中継される。時間は午前10時~午後5時。入場無料。特設ホームページで申し込むと簡単に入場できる。
浪江町地域スポーツセンターでは参加チームがドローンの準備をする様子を見学できるほか、モニターで競技を観戦できる。11、12の両日は子ども向けミニドローン操縦体験会が開かれる。