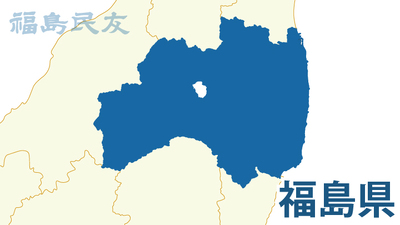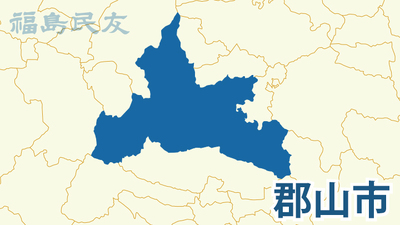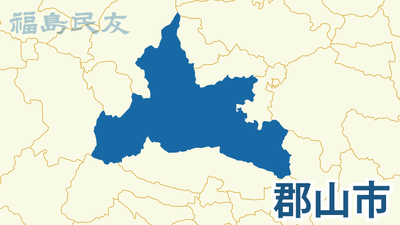法相の諮問機関である法制審議会の部会で、自動車運転処罰法が定める危険運転致死傷罪の要件のうち、速度や飲酒の基準数値を明示した新制度のたたき台が明らかになった。法務省は年内に行われる見通しの部会の結論とりまとめを受け、法改正を目指す。人命を奪いかねない無謀な運転の抑止と、被害者側の悲しみ、憤りの緩和につなげるかが問われる。
現行制度は、危険運転とみなされる速度や飲酒程度を「進行の制御、正常な運転が困難」であることとしている。ただ、明確な基準がないため、その時、運転手が車の操作が困難だったかの立証が難しく、悪質でも最高刑20年の危険運転ではなく、同7年の「過失運転」が適用されるケースがある。
見直しは、交通事故の被害者の遺族がこうした危険運転罪適用の在り方を問題視していることを受けて始まった。たたき台では、速度超過について制限速度から40~60キロの範囲、飲酒は血液1ミリリットル当たりのアルコール濃度0・5~1ミリグラム、呼気は1リットル当たり0・25~0・5ミリグラム以上の範囲で複数案を示した。ドリフト走行なども危険運転の対象に加えた。
部会では、被害者遺族の代表が現行制度について「(悪質で危険な運転は)一瞬の判断ミスや不注意といった過失とは違う処罰をするのが核心だが、その部分が機能していない」と苦言を呈した。法務省には、基準を設けることがこうした指摘に応え得るものかを十分に吟味し、法改正に反映させることが重要だ。
基準以下でも正常な運転が困難であれば危険運転が適用される。数値基準が「ここまでは危険運転ではない」と誤った理解につながらないよう、法務省は周知を徹底してもらいたい。
郡山市で1月、受験生が赤信号無視の車にはねられ死亡するなどした事件では、地裁郡山支部が危険運転致死傷罪に当たると認定し運転手に懲役12年を言い渡した。
地裁は死者が複数ではないことなどから「最も重い部類ではない」として、検察側の求刑した懲役16年より軽い刑とした理由を示した。遺族は量刑に不服を示したが、検察側、被告側とも控訴せず判決が確定した。
危険運転罪ができた背景には、悪質運転で人を死亡させたことに対する処罰が不十分との遺族らの声があった。危険運転の基準が設けられても、同罪の量刑に対する不満の解消にはつながらない。法務省などには法改正と並行して、同罪創設の趣旨に沿った運用の在り方を探ることも求められる。